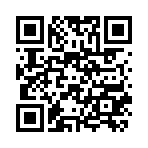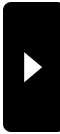2012年07月30日
東京・向島 (3)

今月下旬、墨田区向島を歩きました。

東向島にある “鳩の街商店街”。ここは昔、赤線地帯でした。

上の写真と同じ家。古い家で、喫茶店をやっている。

“鈴木荘” というのは、新規企業に部屋貸しをしている。

鳩の街商店街を後にして歩いていると、榎本武揚の
住居跡があった。

隅田川の土手下の “長命寺”。さくら餅で有名。

長命寺のとなり “弘福寺”(黄檗宗)。
写真は “大雄宝峰殿”、重要文化財。

弘福寺の門、内側から

東向島にある “鳩の街商店街”。ここは昔、赤線地帯でした。

上の写真と同じ家。古い家で、喫茶店をやっている。

“鈴木荘” というのは、新規企業に部屋貸しをしている。

鳩の街商店街を後にして歩いていると、榎本武揚の
住居跡があった。

隅田川の土手下の “長命寺”。さくら餅で有名。

長命寺のとなり “弘福寺”(黄檗宗)。
写真は “大雄宝峰殿”、重要文化財。

弘福寺の門、内側から
Posted by ray at
13:17
│Comments(0)
2012年07月28日
真夏の散歩

散歩の道端にある草木

サンゴジュ(珊瑚樹) 秋にはこの実が赤く色づく

サンゴジュ

アベリアの花 花の期間が長い。臭いが強烈。

メタセコイアの葉 スギ科、メタセコイア属

このメタセコイアは大きくない。

カシの葉を逆光で撮った。
逆光のため葉の形、葉脈がはっきり見える。

サルスベリ(百日紅) ミソハギ科、サルスベリ属

サルスベリ 花の少ない真夏に貴重

ユリノキ(百合の木)の葉 モクレン科、ユリノキ属
別名半纏木、葉の形が半纏に似ている。又はやっこさんに。

サンゴジュ(珊瑚樹) 秋にはこの実が赤く色づく

サンゴジュ

アベリアの花 花の期間が長い。臭いが強烈。

メタセコイアの葉 スギ科、メタセコイア属

このメタセコイアは大きくない。

カシの葉を逆光で撮った。
逆光のため葉の形、葉脈がはっきり見える。

サルスベリ(百日紅) ミソハギ科、サルスベリ属

サルスベリ 花の少ない真夏に貴重

ユリノキ(百合の木)の葉 モクレン科、ユリノキ属
別名半纏木、葉の形が半纏に似ている。又はやっこさんに。
Posted by ray at
13:49
│Comments(0)
2012年07月26日
東京・向島 (2)

前回に引き続き、向島散策

向島百花園からスカイツリーはこのように見える。

百花園内にある石碑の一つ。写真ではよくわからないが、
実は碑面には竹の絵がかいてある。

萩のトンネル。秋になって花が咲いたらどんなだろう。

この蓮を “チャワンハス” というらしい。

白鬚神社

白鬚神社の境内にある 「岩瀬忠震(いわせただなり)」の
碑。岩瀬は幕末の幕臣で外交官。日米修好通商条約の
実質上の締結者

向島に残る商店街 “鳩の街商店街”

同商店街で

向島百花園からスカイツリーはこのように見える。

百花園内にある石碑の一つ。写真ではよくわからないが、
実は碑面には竹の絵がかいてある。

萩のトンネル。秋になって花が咲いたらどんなだろう。

この蓮を “チャワンハス” というらしい。

白鬚神社

白鬚神社の境内にある 「岩瀬忠震(いわせただなり)」の
碑。岩瀬は幕末の幕臣で外交官。日米修好通商条約の
実質上の締結者

向島に残る商店街 “鳩の街商店街”

同商店街で
Posted by ray at
14:37
│Comments(0)
2012年07月24日
東京・向島 (1)

今月下旬、墨田区の向島へ行きました。

東武鉄道の旧業平橋駅は、改名して 「とうきょうスカイツリー」

東向島駅で降りて少し歩いていたら、大きくて美しい葵の花。

向島百花園。文化・文政期(1,804~1,830年)に日本橋で
骨董商を営んでいた佐原何某という粋人がここに土地
3,000坪で花園を開いたのが始まり。3,000坪=1町歩
=3反歩=1ヘクタール=10,00平方米と覚えておくといい。
当時と面積は変わっていない。あまり広くはなく、全部回って
も疲れない。

この季節、花は少ない。これはみたとおり、キキョウ。

むくげ
 百花園内の池
百花園内の池



東武鉄道の旧業平橋駅は、改名して 「とうきょうスカイツリー」

東向島駅で降りて少し歩いていたら、大きくて美しい葵の花。

向島百花園。文化・文政期(1,804~1,830年)に日本橋で
骨董商を営んでいた佐原何某という粋人がここに土地
3,000坪で花園を開いたのが始まり。3,000坪=1町歩
=3反歩=1ヘクタール=10,00平方米と覚えておくといい。
当時と面積は変わっていない。あまり広くはなく、全部回って
も疲れない。

この季節、花は少ない。これはみたとおり、キキョウ。

むくげ
 百花園内の池
百花園内の池

Posted by ray at
12:10
│Comments(0)
2012年07月22日
奈 良 (8)

7月4日、5日 奈良へ行きました。

葛城山・959mへはケーブルカーで登る。その登り口に
ある大きな砂防堰堤。


ケーブルカー終点から、10数分歩くと山頂

葛城山頂の三角点

山頂から少し下ったところにあるロッジ、宿泊ができる。

帰途、ロープウエイ山頂駅

帰り、京都駅まで来た。京都駅正面口の上から。

葛城山・959mへはケーブルカーで登る。その登り口に
ある大きな砂防堰堤。


ケーブルカー終点から、10数分歩くと山頂

葛城山頂の三角点

山頂から少し下ったところにあるロッジ、宿泊ができる。

帰途、ロープウエイ山頂駅

帰り、京都駅まで来た。京都駅正面口の上から。
Posted by ray at
14:17
│Comments(0)
2012年07月20日
奈 良 (7)

7月4日、5日奈良へ行きました。

奈良盆地の西南部・葛城の道を歩いていました。
雨でした。花が雨のしずくを留めています。

葛城山の麓にある “九品寺(くほんじ)”。浄土宗のお寺です。

九品寺には千体石仏と言われている石仏があります。

千体石仏は1,600体、1,700体あると言われ、南北朝時代
に作られたものです。約200年前、境内の竹やぶから発掘さ
れました。

ここに纏めて安置されています。

上の写真の左側部分

この場所の頭上にはカエデの緑。秋には紅葉する。

九品寺をあとにして、田圃の道。農家の白壁が目立つ。

昼食の柿の葉すし。見えているのは鮭。

奈良盆地の西南部・葛城の道を歩いていました。
雨でした。花が雨のしずくを留めています。

葛城山の麓にある “九品寺(くほんじ)”。浄土宗のお寺です。

九品寺には千体石仏と言われている石仏があります。

千体石仏は1,600体、1,700体あると言われ、南北朝時代
に作られたものです。約200年前、境内の竹やぶから発掘さ
れました。

ここに纏めて安置されています。

上の写真の左側部分

この場所の頭上にはカエデの緑。秋には紅葉する。

九品寺をあとにして、田圃の道。農家の白壁が目立つ。

昼食の柿の葉すし。見えているのは鮭。
Posted by ray at
14:04
│Comments(0)
2012年07月18日
奈 良 (6)

7月4日、5日 奈良へ行きました。

一言主神社へ立ち寄ったあと、次に見る “九品寺” まで
少し歩いた。この地は古墳時代の有力豪族の葛城氏が
活躍したた場所で、当時の幹道・葛城の道が存在します。
このような立派な農家がありました。

このような大きな屋敷と立派な入母屋の屋根も。

葛城の道などを示す標識

この田圃の中の道が、葛城の道として実証されたのかどうか?

棚田の向こうは奈良盆地

第2代の “綏靖(すいぜい)天皇”の宮址の標識

再び奈良盆地を望む

路傍にて。花をだれが供えたか。

葛城の道を歩く。

一言主神社へ立ち寄ったあと、次に見る “九品寺” まで
少し歩いた。この地は古墳時代の有力豪族の葛城氏が
活躍したた場所で、当時の幹道・葛城の道が存在します。
このような立派な農家がありました。

このような大きな屋敷と立派な入母屋の屋根も。

葛城の道などを示す標識

この田圃の中の道が、葛城の道として実証されたのかどうか?

棚田の向こうは奈良盆地

第2代の “綏靖(すいぜい)天皇”の宮址の標識

再び奈良盆地を望む

路傍にて。花をだれが供えたか。

葛城の道を歩く。
Posted by ray at
13:25
│Comments(0)
2012年07月16日
奈 良 (5)

7月4日、5日 奈良へ行きました。

高天彦神社(たかまがひこじんじゃ)に到着しました。
ここは金剛山の東麓、天孫降臨の高天原と信じられています。

同神社の門前

両側に杉の大木がある参道

真っ白い紫陽花が咲いていた。

これも神社の門前、蛙の形の石

今度は一言主神社(ひとことぬしじんじゃ)に。

同神社拝殿

同扁額

同神社の境内にある “ちちいちょう”

ちちいちょう の幹。たれさがっている気根に名の由来がある。

高天彦神社(たかまがひこじんじゃ)に到着しました。
ここは金剛山の東麓、天孫降臨の高天原と信じられています。

同神社の門前

両側に杉の大木がある参道

真っ白い紫陽花が咲いていた。

これも神社の門前、蛙の形の石

今度は一言主神社(ひとことぬしじんじゃ)に。

同神社拝殿

同扁額

同神社の境内にある “ちちいちょう”

ちちいちょう の幹。たれさがっている気根に名の由来がある。
Posted by ray at
10:49
│Comments(0)
2012年07月14日
奈 良 (4)

7月4日、5日 奈良へ行きました。

船宿寺(せんしゅくじ) 奈良県御所市にある真言宗のお寺。
非常に美しく整備されている。
つつじ、ぼたん、山吹などの花で有名。

船宿寺に咲いていた紫陽花

同じお寺

住職さんのお話。主として庭について、ここは遠州流の
回遊式庭園。

その庭園

御所市(ごせし)の案内所にて、床に当市の地図。

高鴨神社の池

同神社の舞の舞台

同神社

神社の池

船宿寺(せんしゅくじ) 奈良県御所市にある真言宗のお寺。
非常に美しく整備されている。
つつじ、ぼたん、山吹などの花で有名。

船宿寺に咲いていた紫陽花

同じお寺

住職さんのお話。主として庭について、ここは遠州流の
回遊式庭園。

その庭園

御所市(ごせし)の案内所にて、床に当市の地図。

高鴨神社の池

同神社の舞の舞台

同神社

神社の池
Posted by ray at
16:25
│Comments(0)
2012年07月12日
奈 良 (3)

7月4日、5日 奈良

橿原考古学研究所付属博物館 手前は石棺、向こうは陶棺

飛鳥板葺宮 模型

同 上

橿原神宮 明治23年、官幣大社として創建された。
主祭神は神武天皇。


巨大な手水鉢



橿原市内の塚、久米仙人が落下したところという言い伝え
があるところ

夕暮れ、陽は既に沈んでいる 畝傍山がシルエット

橿原考古学研究所付属博物館 手前は石棺、向こうは陶棺

飛鳥板葺宮 模型

同 上

橿原神宮 明治23年、官幣大社として創建された。
主祭神は神武天皇。


巨大な手水鉢



橿原市内の塚、久米仙人が落下したところという言い伝え
があるところ

夕暮れ、陽は既に沈んでいる 畝傍山がシルエット
Posted by ray at
13:00
│Comments(0)